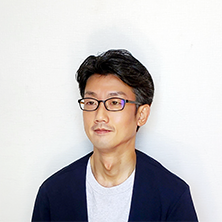医院開業コラム
開業のタネ
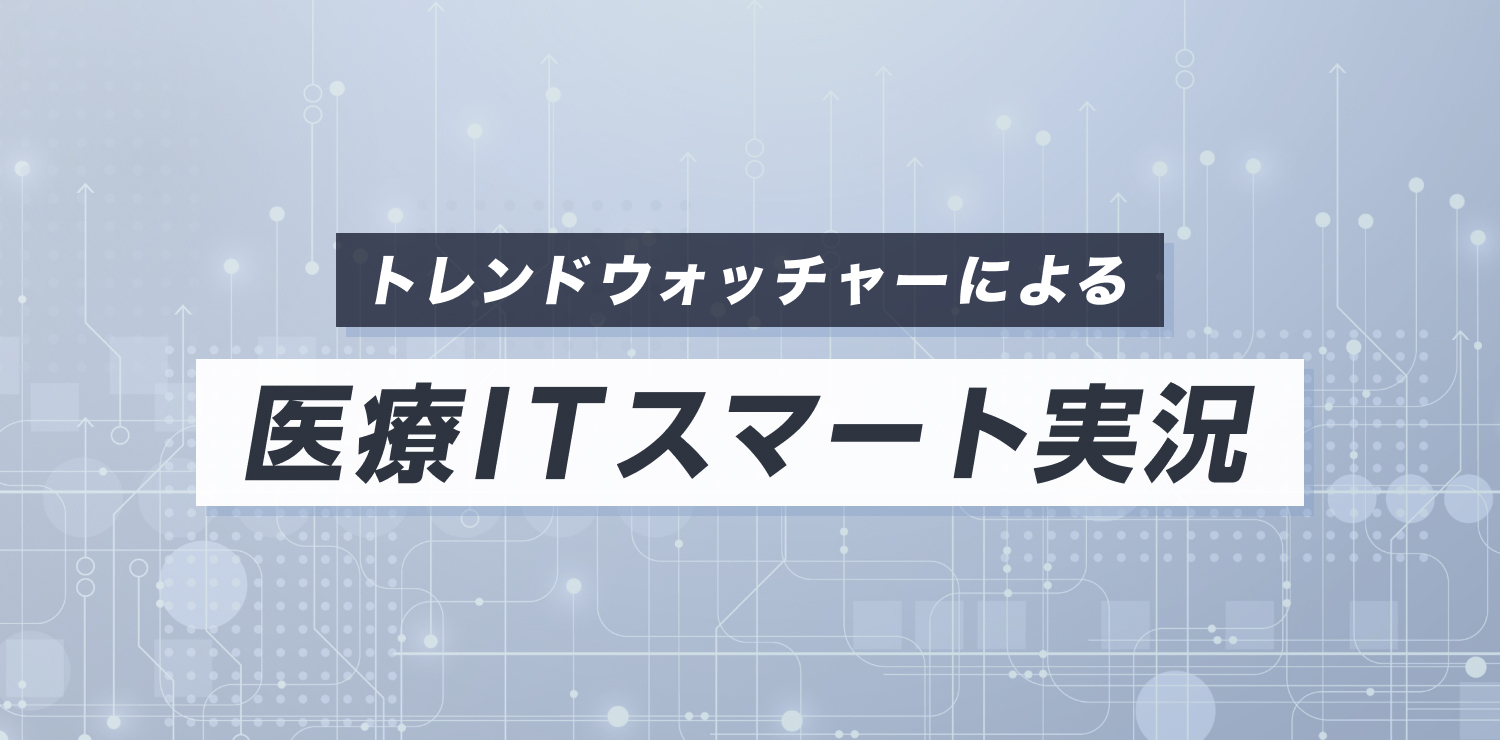
トレンドウォッチャーによる医療ITスマート実況 第5回
クリニックにおけるITトレンド(Web問診編)
- 医院開業のポイント
2025.04.22
受付スタッフの採用・労務問題にお悩みのクリニックは非常に多く、受付周りの業務効率化と負担の削減は避けて通れない経営課題になっています。なかでも、問診に関する業務は「ムダ」が多いですが、その一方、効率化しやすい業務でもあります。
第5回では、Web問診にスポットを当て、システムの種類や選定方法をはじめ、導入効果、メリットなどを、お伝えしていきます。
問診業務の現状
現在、電子カルテの普及率は約50%に達しています。しかし、いわゆるWeb問診サービスが登場してから10年は経過しているにもかかわらず、紙の書類をスキャンする手間が発生しているクリニックが非常に多いのが現状です。
『日経メディカル開業サポート』が行った「Web問診の普及率と導入意識」の調査によると、Web問診システムの「導入率」は2~3%、「導入しようと思っている」および「制度や補助金次第で検討したい」という前向きな回答を加えても、33%程度という結果になっています。ただ、この数年は「予約システムのオプションとして手軽に導入できるようになった」など、ハードルが下がったことで導入が加速しています。
※出典:『日経メディカル開業サポート』Web問診の普及率と導入意識分析https://nm-kaigyo.nikkeihr.co.jp/career_labo/practice/014/https://nm-kaigyo.nikkeihr.co.jp/career_labo/karte_enquete/013/?esid=92I3sZOx3xsmsntIxKtog25IS3hGkdHogakeT0ux66QzjzE0GjwBwVjPVXqI-7oO&explicit=0
問診業務の効率化はWeb問診の大きなメリット
では、実際に紙問診とWeb問診を比較し、業務フローをどれだけ効率化できるか見ていきましょう。それぞれのおおまかな業務フローは、以下のようになります。
紙問診の業務フロー
①患者さんが来院→②問診票を渡す→③患者さんが問診票を記入→④問診票を受け取る→⑤問診票をスキャンして電子カルテに取り込む
※スキャン以外に回答を電子カルテに転記入力する方法もある
- 問題点
・リアルタイムでスキャンや転記する時間が取れないため、紙の問診票を回して診察し、診療後にまとめて取り込むという事態になりやすい(残業発生要因)
・どの患者さんにも画一的な問診になり、結局診察時に再確認している
Web問診の業務フロー
・来院予約ありの場合
①患者さんがスマホで予約入力→②そのままWeb問診を入力→③スタッフが電子カルテにコピー&ペースト
・来院予約なしの場合
①患者さんがQRコードを読み取る→②スマホでWeb問診を入力→③スタッフが電子カルテにコピー&ペースト
このように、Web問診にすることで来院後に問診票を記入する時間の削減、回答を電子カルテへ取り込む時間の削減が可能です。仮に患者さん1人あたり3分の時間短縮ができたとして、50人分で150分、100人で300分の短縮になります。この短縮は、残業リスクの低下とホスピタリティの向上にもつながります。空いた時間でほかの業務を行うことも可能ですし、何よりスタッフに余裕ができ患者応対の質を上げられることが重要ではないでしょうか。
Web問診システムの種類
ここまで、Web問診の導入効果とメリットについて述べてきました。次に、Web問診システムにはどのような種類があるのか見ていきましょう。
(さらに…)
この記事をシェアする