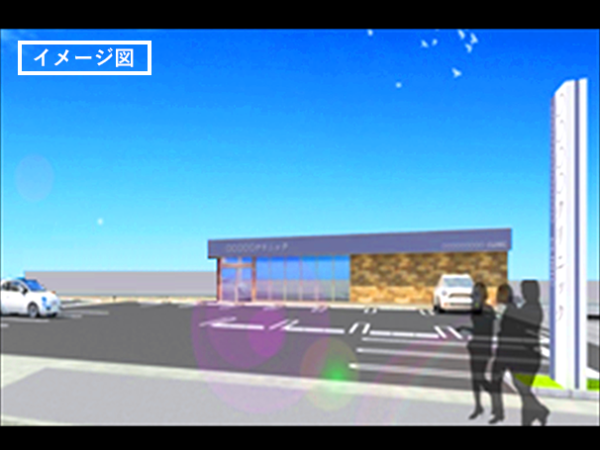医院開業コラム
開業のタネ

FP佐久間のみらいマネー研究所 第7回
「法人保険」の基礎知識と留意点
- 財務・経理・会計
2018.03.26
前回まで、個人で加入する生命保険における支払い方や、受け取り方に関する税金についてお伝えしてきました。今回からは少し見方を変え、医療法人や株式会社(以下、二つを合わせて法人と呼びます)を経営する方の生命保険について考えていきます。
法人保険の目的と損金算入について
法人を経営する方が生命保険に加入する場合、保険料を法人が負担することができます。これを「法人保険」と呼び、保険契約者は「法人」となります。法人保険の主な用途は以下のものが挙げられます。
1.代表者に万一があっても、法人が無事存続するように加入する事業保障
2.役員・従業員に万一のことがあったときの死亡退職金の支払原資
3.役員・従業員の勇退退職金の積立
法人保険は保険の種類や受取人の設定などにより、法人の損金に算入できる場合があります。まずは保険種別ごとに損金算入の可否を見ていきましょう。
a.一生涯の死亡保障がある終身保険
⇒損金算入不可(全額資産計上)
b.一定期間の死亡保障がある定期保険
⇒損金算入可(タイプや保険期間により全部または一部可)
c.満期保険金がある養老保険
⇒損金算入不可(加入者や受取人の設定により一部損金算入可)
d.医療保険
⇒損金算入可(死亡保障の有無、解約返戻金の有無により不可の場合あり)
e.がん保険
⇒損金算入可(解約返戻金の有無により一部損金算入不可の場合あり)
損金算入は保険の種類や死亡保険金の受取人の設定などにより税務処理のルールが定められているため、注意が必要です。
※詳しくは「法人税基本通達」などを参照してください。
「死亡保障」を法人で確保する場合の留意点
ここで、生命保険のなかでも事業保障や死亡退職金の原資を目的として加入する、いわゆる「死亡保障タイプ」について考えてみます。この場合の生命保険は、次のようなパターンが一般的です。
・保険の種類:定期保険
・保険契約者:法人
・被保険者:理事長、理事、社長、役員など
・死亡保険金受取人:法人
「死亡保障タイプ」は保険料の一部、または全部を損金に算入できるため、多くの法人経営者がこの形の保険に加入されています。
個人で生命保険に加入する場合、生命保険料控除の範囲を超えた保険料は税引き後の可処分所得から支出することになります(第5回参照)。ですから、法人経営者のなかには「損金算入できるのであれば、個人保険より法人保険がいい」と仰る方もたくさんいらっしゃいます。そのため「個人で加入していた生命保険を、すべて法人契約に変更したほうがよいのか」という相談をされることも多いのです。しかし、果たして本当にすべての生命保険を法人契約にしてよいのでしょうか。
上記のケースでいえば、いざ万一が発生した場合には保険金の受取人は「法人」になります。以前お伝えしたように、個人保険はご家族の生活保障などを目的に加入されるものですから、法人契約に変更していたとすると、法人は受け取った死亡保険金をご家族にお渡ししなければなりません。法人からご家族に死亡保険金をお渡しする手段の代表的なものに「死亡弔慰金」「死亡退職金」があり、それぞれ以下のように計算されます。
「死亡退職金」・・・最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率
「死亡弔慰金」・・・最終報酬月額×6ヶ月(業務外)※業務上の場合は36ヶ月
この計算式をもとに、以下のケースにあてはめて算出していきましょう。
【例】法人設立し、理事長に就任して2年目。理事長報酬の月額が150万円のケース。
この場合の死亡退職金は「最終報酬月額150万円×役員在任年数2年×功績倍率3 = 900万円」となります。
※功績倍率を「3」としていますが、設定にはさまざまな考え方がありますので、個別のケースについては顧問税理士や所轄の税務署などにご確認ください。
つまり、法人設立直後に万一のことがあると「死亡退職金」の受け取り金額がご家族の生活保障に到底及ばないことも考えられるのです。生命保険の加入目的が「事業保障」なのか「死亡退職金の原資」なのかなどにより考え方は異なりますが、個人で加入する生命保険と法人で加入する生命保険のバランスを考慮する必要があるでしょう。
では次に、医療保障を法人で確保する場合について考えます。死亡保障と同じく、医療保障についても「法人保険に変更すれば損金になる」と考える方がいらっしゃいますが、実際のところはどうなのでしょうか。
「医療保障」を法人で確保する場合の留意点
多くの場合、医療保険の保険料は全額が法人の損金に算入できますが、入院給付金・手術給付金といった給付金の受取人は法人です。法人契約でも給付金受取人を個人に設定できますが、保険料相当額については被保険者が所得として課税を受けることになります。
医療保険の目的が「治療費の補てん」だとすると、法人が受け取った給付金を、法人からご自身に渡さなくてはなりません。法人として給付金の全部、または一部を役員に渡したいと考えたとしても、社会通念上の見舞金の範囲を超えた金額は役員報酬などとされ、課税を受けてしまうのです。
では、この社会通念上の見舞金の額とはどのくらいなのでしょうか。さまざまな考え方があるので一概にはいえませんが『国税不服審判所の平成14.6.13の裁決事例』では、見舞金の額は50,000円とされています。
『国税不服審判所の平成14.6.13の裁決事例』
http://www.kfs.go.jp/service/JP/63/21/index.html
一方、医療保険を個人で加入している場合は死亡保障と同様に、医療保険料控除の範囲を超えた保険料は税引き後の可処分所得で支払います。しかし、受け取った入院給付金や手術給付金は、基本的には非課税です(所得税法施行令第30条)。
給付金は、個人契約で受け取る場合には非課税になるというメリットがありますので、法人契約にする場合は十分な検討が必要です。
昨今、医療保険の保険料を比較的短期間(10年以内)で払込を終了させて終身の医療保険を確保する提案がなされています。この場合の保険料も全額が損金に算入できると考えられており、法人契約をされる方も多くなっています。このタイプは払込期間の経過後に個人契約に変更する(その時点の解約返戻金で譲渡する)などの手段を含めて検討することで効果が高くなるケースもありますので、法人保険に詳しいFPなどにご相談されるとよいでしょう。
※税務の取り扱いは2018年3月現在の税制を基準としていますが、個々の具体的な税務の取り扱いについては顧問税理士や所轄税務署などにご確認ください。
※このコラムは、2018年3月現在の情報をもとに執筆しています。
この記事をシェアする