開業した先生の声
開業サポート実績
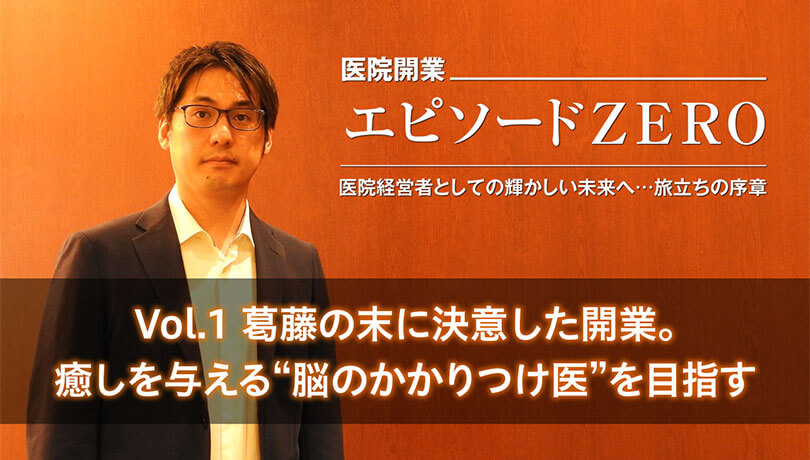
Vol.1
葛藤の末に決意した開業。癒しを与える“脳のかかりつけ医”を目指す
- 医院開業エピソードZERO
2020.10.19
クリニックの開業を目前に控えたドクターが、今何を考え、悩み、いかにして困難に立ち向かったのか……そんな開業の準備期間、いわば“エピソード・ゼロ”にフォーカスする本シリーズ。巷にあふれる成功体験記ではなく、開業医の序章を紐解くことで、よりリアルなクリニック開業に迫ります。
初回は、大阪市城東区の医療モール「クリニックステーション野江」に開業される脳外科医の岩田 亮一先生にお話を伺いました。「脳のかかりつけ医になりたい」と話す岩田先生の“始まりの物語”を紐解きます。
気軽にMRI検査が受けられる“脳のかかりつけ医”を目指す
「いわた脳神経外科クリニック」が掲げる理念について教えてください。
当院の理念は、「脳を守る」です。その実現のためには、病気を早期発見、治療をできる環境づくりが必要。そこで私たちは、“脳のかかりつけ医”として、地域の方々と密接に関わっていきたいと考えています。同時に開院後も最新の医学を学び続け、最新設備を整えた先進的な医療を行いたいと考えています。
“脳のかかりつけ医”として、具体的にどのような医療サービスを提供していく予定ですか?
まずは、体の些細な異常にもいち早く気づくために、MRI検査を気軽に受けてもらえるようにします。そして何より、脳に関係する可能性がある悩みについて“気軽に話せる窓口”として機能したいですね。例えば頭痛やめまいなど、脳とは関係ないかもしれないけど、「ちょっと不安」という段階でぜひ来院してもらえたらと思います。
脳神経外科と聞くとハードルが高く感じてしまう方も少なくないと思いますが、私は“脳外科医と患者”である前に“人と人”としてお付き合いをしていきたいので、遠慮なく頼ってもらえたらうれしいです。私は幼少期からおじいちゃんになついていて、山や川によく連れて行ってもらいました。その祖父がパーキンソン病を患ったときに、MRI設置のクリニックを開業してほしいと懇願されたんですね。開業前には他界してしまいましたが、いまはそれが実現されます。皆さんが安心して自分らしく人生を楽しみ、そして人生の目標を達成する……そのお手伝いができるクリニックを目指していきたいです。

患者さんの悩みに寄り添う治療をするべく開業を決意
岩田院長が医師、そして脳外科医を志したきっかけを教えてください。
私が医師を目指すようになった最も大きなきっかけは、中学1年生のときに阪神淡路大震災を経験したことです。全壊した家から命からがら逃げ出すとき、ガラス片で足にケガを負ってしまって、近所の病院に駆け込みました。結果的には無事に傷口を縫合してもらえましたが、その際に医師から「これが最後の縫合糸だった」と言われて……。もし縫合糸がなくて、あのまま血が止まらなかったらと考えると、ものすごい恐怖に襲われました。身をもって医療のありがたみを実感した出来事でした。
それから、以前父が病気を患って外科医の先生にお世話になったことも、医師への憧れを強めたきっかけです。外科医の道を進んだのは、研修医時代にさまざまな治療の現場を見るなかで、「目の前に倒れている人を自分の手を動かして助けられる医者になりたい」と考えるようになったのが理由です。
そして、どうせ外科医をやるなら難しい病気を治したいと思い、脳外科を選びました。脳はとても繊細な臓器で、一度損傷すると再生することはありません。しかも脳の病気は日常生活の動作に影響を与えることが多く、その治療は患者さんのQOLを大きく左右します。プレッシャーもありますが、非常にやりがいのある仕事だと感じています。

[執刀をされる岩田院長]
医師以外の側面では岩田院長はどのような方なのですか?
これまでは四六時中、患者さんのこと、手術のこと、研究のことばかりを考えて生きてきました。設計士の妻と共働きなのですが、家事はほとんど任せっきりで申し訳ないと思っています。仕事柄、常に緊張を強いられるのでジョギングや読書などで気分転換を図ることが多いです。休みの日に子どもと外出することが一番の楽しみですね。
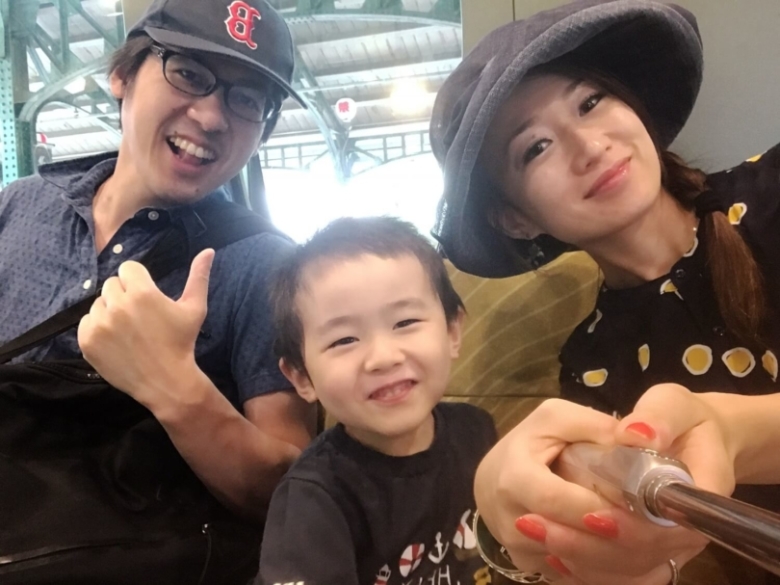
[ご家族揃ってお出かけの一枚]
大学病院を離れ、自身のクリニックを開業することに決めたのはなぜですか?
この記事をシェアする





